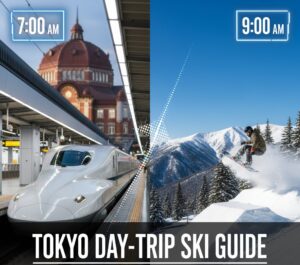冬の週末、私たちが当たり前のように楽しんでいるスキー場。 真っ白なゲレンデ、山頂まで運んでくれるリフト、冷えた体に染みるゲレ食のラーメン…。
しかし、ふと疑問に思ったことはありませんか?
「この広大なスキー場って、一体『誰が』『なんのために』作ったんだろう?」
リフト券売り場の隅に書かれた運営会社の名前を見ても、ピンとこないかもしれません。 ですが、その歴史を紐解くと、そこには「鉄道会社」の戦略、「楽器のヤマハ」の挑戦、そして「バブル経済」の熱狂と崩壊、さらには「海外ファンド」の進出という、日本の近代史そのものが隠されているのです。
この記事では、あなたが知っている「あのスキー場」の意外な誕生秘話と、開発のウラ側を分かりやすく解説します!
すべては「鉄道」から始まった。日本のスキー場開発「第1世代」
今でこそ「スキーは車で行くもの」というイメージが強いですが、日本のスキー場の黎明期(戦前〜高度経済成長期)、主役は「鉄道会社」でした。
キーフレーズ:「スキー場は、電車で行く場所だった」
- なぜ鉄道会社が? 答えはシンプルで、「冬の閑散期に、鉄道(電車や新幹線)に乗ってほしかったから」です。 当時のスキー用具は重く、車で雪道を行くのも大変でした。そこで鉄道会社は「駅の近くにスキー場を作れば、冬でも観光客が鉄道を使ってくれる!」と考えたのです。
- 代表的な開発会社:
- 東急グループ(現:東急リゾーツ&ステイ株式会社): 今も昔も「白馬エリア」の開発に深く関わっています。白馬八方尾根、白馬五竜、栂池高原など、名だたるスキー場のリフト会社やホテル運営に東急が関わっているのは、首都圏から人々を運ぶ「鉄道」と「スキー」をセットで考えていた名残です。
- JR東日本(旧:国鉄): 国鉄も観光開発に積極的でした。その究極の形が、新潟県の「GALA湯沢」です。なんと新幹線の駅(ガーラ湯沢駅)の改札が、そのままスキー場のゴンドラ乗り場に直結しています。これは「鉄道客を呼ぶ」という目的を最も象徴するスキー場と言えます。
【発見!】この会社も!? バブルと異業種参入の時代
1980年代後半、日本は空前のスキーブームに突入します。 1987年の映画『私をスキーに連れてって』の大ヒットと、バブル経済の絶頂期が重なり、スキーは「若者のトレンディな遊び」の象徴となりました。
キーフレーズ:「作れば儲かる!日本中がスキー場開発に熱狂」
この時代、主役となったのは鉄道会社だけではありません。「総合デベロッパー」と「異業種からの参入組」です。
- 代表的な開発会社:
- 西武グループ(現:株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド): この時代の「リゾートの王様」です。「苗場」「かぐら」「万座温泉」「富良野」など、今も人気の巨大スキー場を次々と開発・運営。苗場プリンスホテルとユーミンのコンサートは、当時のスキーブームの象徴でした。
- ヤマハ(楽器・バイクメーカー): 北海道の「キロロリゾート」を開発。「なぜヤマハが?」と驚きますが、体力のある大企業が「リゾート開発」という未来の事業に夢を見て参入した、バブル期らしい例です。(※現在は経営が移管されています)
- ソニー創業者一族の関連会社(当時): 新潟県に「ARAI MOUNTAIN & SPA」(現:ロッテアライリゾート)を1993年にオープン。これも異業種参入の代表格です。 (同リゾートは2006年に経営破綻し、長期間閉鎖された後、2015年に「韓国ロッテグループ」(ホテルロッテ)が買収し、2017年に「ロッテアライリゾート」として再オープンするという稀有な歴史をたどります。)
「そうだったんだ!」ポイント: 楽器の会社までが、本業とは全く違う「スキー場」という巨大なハコモノ開発に乗り出すほど、当時の日本はスキーに熱狂し、景気が良かったのです。
ブームの終焉と苦悩。「統廃合」と「経営難」の時代
楽しい宴は長くは続きません。 1990年代後半から、バブル崩壊、スキー人口の減少(若者のレジャー多様化)、そして少子化のトリプルパンチがスキー場を襲います。
キーフレーズ:「ブームが去り、スキー場が多すぎた」
スキー人口は、ピーク時(1993年)の約1,800万人から、現在は500万人以下(3分の1以下)に激減しました。 作られすぎたスキー場は、莫大な維持費(リフトの点検、圧雪車、人件費)を払えず、次々と経営難に陥ります。
- 主な動き:
- ヤマハやロッテなど、「異業種参入組」は本業に集中するため、赤字のリゾート事業から次々と撤退。(アライリゾートもこの時期に閉鎖されました)
- リゾートの王様「西武グループ」も解体。多くのスキー場がバラバラに売却されました。
- 全国でスキー場の閉鎖が相次ぎ、「あのスキー場、昔はあったのに…」という場所が増えていきました。
黒船来航!「JAPOW」が世界に見つかった外資系の時代
経営難に陥った日本のスキー場。しかし、そこに新たな価値を見出した者たちが現れます。それが「海外の投資ファンド」です。
キーフレーズ:「日本の雪は世界一。なのに、スキー場が(彼らにとって)タダ同然で売られていた」
特に北海道や白馬の雪は「JAPOW(ジャパウ)」と呼ばれ、その軽さと量から世界中のスキーヤーの憧れでした。 彼ら海外資本は、「こんなに素晴らしい雪があるのに、リゾート施設(ホテルや食事)が古すぎる。ここを『世界基準』に作り替えれば、世界中から富裕層を呼べる!」と考えたのです。
- 代表的な動き:
- ニセコ(北海道): オーストラリアを始めとする海外資本が次々と進出。古いペンションや民宿が取り壊され、超高級なコンドミニアムや外資系ホテル(リッツ・カールトンなど)が立ち並ぶ街並みに変貌しました。今や「日本で最も外国な場所」の一つです。
- 星野リゾート(国内企業): 「外資」とは違いますが、経営難に陥ったスキー場(アルツ磐梯、トマムなど)を、独自のブランド力で見事に再生させた代表格です。
- ロッテ(まさかの再オープン): かつて(ソニー関連会社などによって)開発されたものの経営破綻し、長期間閉鎖されていた「アライリゾート」の跡地を、2015年に韓国ロッテグループ(ホテルロッテ)が公売で新たに取得。2017年に超高級リゾート「ロッテアライリゾート」として復活させるという、非常に珍しいケースもあります。
「そうだったんだ!」ポイント: 「最近、ニセコや白馬がおしゃれになった」「外国人が増えた」と感じる理由は、こうした海外資本や大手リゾート運営会社が、古いスキー場を「国際リゾート」として大規模に作り替えているからなのです。
まとめ:今のスキー場は、誰が運営しているの?
現在、日本のスキー場は、大きく分けて以下の4つの勢力によって運営されています。
- 外資系・ファンド系: (ニセコ、白馬の一部、キロロなど) 莫大な投資で、世界基準の高級リゾート化を進める。
- 国内大手リゾート系: (プリンスホテル(旧西武)、星野リゾート、ロッテなど) 強力なブランド力とサービスで、質の高い滞在を提供する。
- 古参の鉄道会社系: (東急、JR東日本など) 古くからの優良スキー場を、安定的に運営し続けている。
- 地場・ローカル系: (野沢温泉、蔵王など) 古くから「村営」や「地元の企業」が、伝統を守りつつ堅実に運営。
次にスキー場に行くときは、リフトマップの隅に書かれている「運営会社」の名前をちょっとだけ見てみてください。 「ここはプリンス系か。昔の西武だな」「ここは東急系か、鉄道の名残だな」 そんな風に考えると、ただ滑るだけでは見えてこなかった、スキー場の「個性」や「歴史」が感じられるかもしれませんよ。